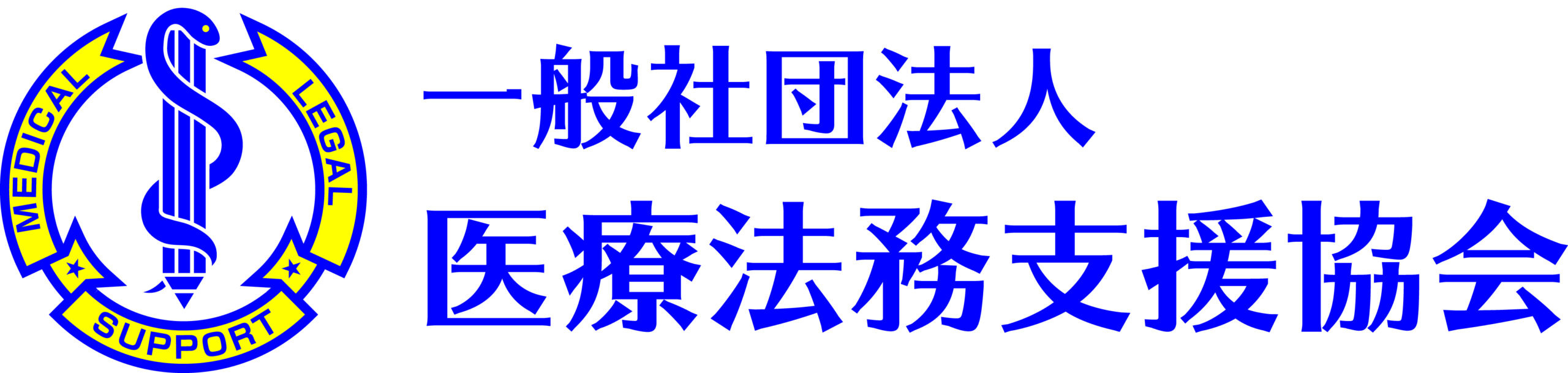「医療法人の設立」と一言で言っても、実際にはどのような手続が必要なのでしょう。医療法人を設立するためには、「認可」が必要ですし、文字どおり「設立」だけをしても空っぽの箱ができるだけです。認可を得て設立して、そのあとの個人から法人への切替こそが重要になります。
いわゆる医療法人の設立手続とはどのようなものなのか、全体を見通していただきたいと思います。
医療法人設立のために検討すべきこと
医療法人を設立するためには、まず以下の人的要件をクリアすることが必要です。
- 医師または歯科医師であること
- 欠格条項(医療法第46条の2第2項)に該当していないこと
- 理事3名以上、監事1名以上の役員(医療法第46条の2第1項)
- 社員3名以上
そして、当然のことながら「医療機関を開設すること(医療法第39条第1項)」が必要です。
医療法人の設立認可
- 年に数回の申請受付期間
- 医療審議会が認可
まず、一番はじめに必要なのは、医療法人の設立認可を得ることです。
各自治体が窓口となりますが、いつでも受け付けてくれるところはむしろ少なく、年に数回のみ受付期間があるのが普通です。
たとえば、東京都の場合は以下のようなスケジュールです(H24年度参考)。
| 7月頃 | 事前説明会(年1回) |
| 9月頃 | 第1回仮受付(期間は約1週間) |
| 12月末頃 | 本申請 |
| 2月頃 | 医療審議会 |
| 2月中旬 | 認可 |
| 第2回仮受付 | |
| 認可 |
医療法人の設立登記
認可書が取得できましたら、それに基づいて登記をします。
窓口(申請先)は、法務局です。最近、商業・法人登記の管轄が集約されている県が多いので、必ず確認してください。
Q登記は、認可書を受け取ってから2週間以内にしなければなりませんか?
2週間の起算点は、「設立のための手続がすべて終了した日」からです。
したがって、実際に認可書を受け取ったのは2月15日だとしても、登記の申請は4月1日ということもあり得るわけです。
逆に、2週間以上待ってから申請しなければならないケースもあります。事業年度末日が3月末日にもかかわらず3月中に登記申請した場合、1ヶ月も経たないうちに第1期目が終わってしまうことになりかねません。
Q認可されたら設立登記・・・そのあとは?
認可書が交付されれば、医療法人の設立登記の申請をすることができます。管轄の法務局へ申請し、1週間前後で登記事項証明書(と、法人の印鑑証明書)が取得できるようになるでしょう。法人自体は、設立登記を申請した日から誕生することになります。
しかし、単に登記だけしても空っぽの箱に過ぎません。これまで個人として開設していた診療所を、法人としての開設に切り替える作業が必要です。むしろこれからが本番というわけです。
まず、法人の場合、開設の前に【診療所開設許可申請】が必要です。月内に申請して、翌月1日付けで許可が出ます。ただし、立入検査があることを忘れないでください。余裕を持って申請するようにしましょう。
許可と同時に開設届が受理されるようになり、医療法人としての診療がスタートします。
ところがこれで終わりではありません。
保険医療機関の指定申請が必要です。自治体によって期限が異なりますので、しっかり確認してください。期限を逃してしまうと、丸1ヶ月、保険診療ができないことになってしまいます。自由診療のみであれば不要ですが、医療保険診療をする場合には必ず必要になります。
切り替わる時期ですが、個人から法人への移行の場合は遡及が認められます。新規の際には申請の翌月1日からの指定でしたが、遡及願を書いて、開設日まで遡って保険診療できるようにします。
なお、新たな医療機関コードは月末にならないと届きません。保険請求事務の際はご注意ください。
さて、基本的にはこれでいよいよ医療法人としての診療がスタートできる状態になったわけですが、施設基準の指定や各種専門医の指定などを受けている場合、麻薬免許をお持ちの場合など、それぞれ個人→法人への変更手続があります。これらは、廃止・指定の場合と変更の場合がありますので、それぞれの手続に応じて書類を提出してください。
以上のように、認可取得後にこそ、医療法人化が始まるといえます。しかも、期限が厳密ですので、よく確認して進めていかないと大変なことになりかねません。どうぞご注意ください。
診療所開設者の切替
保険医療機関の切替
医療法人設立のタイミング
個人で診療所を開設して、患者数も伸びてきたら、医療法人化は誰しも考えることです。売上げが増えて節税を意識し始めれば、個人と医療法人のどちらがよいかは気になりますよね。
しかし、医療法人化の適切なタイミングについては個別具体的な検討が必要であり、売上げだけで判断することはできません。いったん医療法人を設立したら、簡単に辞めるわけにいきません。売上げが下がったからやっぱり・・・というわけにはいかないのです。
従って、売上げだけを見るのではなく、開設からの年数や今後の見通しについても考え合わせることをご提案しています。
個人開設から2年以上たち、今後もその場所で続けていけるのであれば、やはり法人化をお勧めします。しっかり腰を据えて診療に専念していくためには、基盤として法人であるほうがよいでしょう。
また、個人の課税はその一人に対して従量制でどんどん増えていき、半分まで持って行かれてしまいますから、ノーガードですべて真正面から受けることになりますが、法人であれば工夫のしようもあります。そうした点からも、できるだけ早めに検討し、準備を進めていくことが重要です。
平成19年の改正で何が変わったか
いわゆる第5次改正により、医療法人制度は大きく変わりました。
特に、持分のある医療法人設立ができなくなり、これまで以上に「法人にすれば節税になる」と単純には言えなくなっています。将来的なことも考えた上での移行が、より重要性を増しています。移行前の準備も、より重要になっています。あるがままに法人化を進めても、こんなはずじゃなかった・・・ということになりかねません。
参考)医療法人制度の主な改正点について(東京都福祉保健局)
※ 別窓が開きます。
もっとも大きな変更点は、やはり新たに設立できる形態が、「財団である医療法人」・「社団である医療法人で持分の定めのないもの」に限られたということでしょう。今後医療法人を設立する場合、出資した金額以上の払戻しは認められないということが徹底されるのです。基金制度の採否など、慎重に検討する必要があります。
また、既存の法人にとっても重要な点としては、医療法人の管理等に関する事項にあるとおり、「医療法人の内部管理体制の明確化」が強化されたことでしょう。
特に、監事の役割が医療法で明文規定となり、これまで以上に名目だけの役員がないよう、チーム医療だけでなくチーム運営が重要となりました。
この点は、これから設立を考える際にも当然ポイントとなります。一人医師医療法人の設立では、単純に親族を役員にすることはよく考えたほうがよいでしょう。
医療法人の設立認可申請の際に注意すべき点として、地方自治体ごとの違いにも気をつけなければなりません。
東京都では、必須ではないものの、説明会は年に1回しか開催されず、申請時期は3月と9月の年2回しかありません。千葉県では、監事以外にも第三者理事を選任するよう指導があり、説明会にも必ず出席しなければ仮申請すら受理されません。
理想的な医療を実現するために、どのようなことが可能で、どのようなことが必要なのか、しっかりと情報収集していく必要があります。