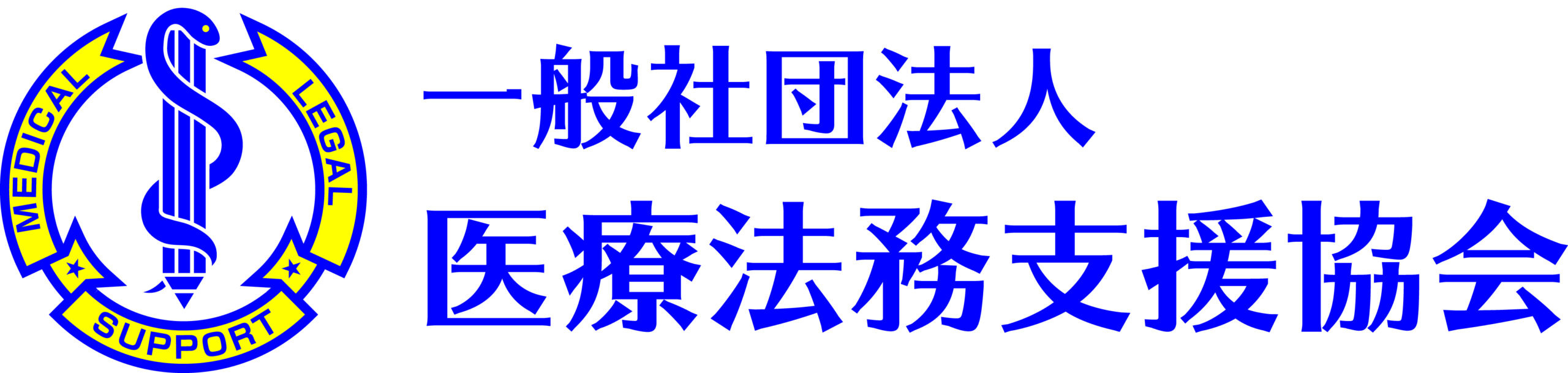定款は、医療法人にとって憲法にあたるものであり、原則となるルールが書かれています。これを変更するためには、社員総会での決議を経て、さらに認可を受ける必要があります。
それほど重要な定款ですが、ほとんどの場合、ほぼモデル定款どおりに作成していると思います。
しかし、内容をしっかり把握していないければならないことは言うまでもありません。それによって、それぞれの医療法人ごとに定款=憲法を決めることもできます。医療法は個別具体的なことまで規定してはいませんので、定款にどのように規定されているかが非常に重要です。
定款には、医療法人の名称や所在地など基本的な内容が書かれていることはもちろんですが、役員の任期や選任方法、会議の種類や運営方法など、医療法人の運営に必要なルールが多数定められています。医療法人運営の大原則となるのが、「定款」というわけです。
定款に定めること
医療法人の定款には、最低限、以下のことが定められていなければなりません
- 目的および業務
- 名称
- 事務所の所在場所
- 代表権を有する者の氏名、住所および資格
- 存続期間または解散の事由を定めたときは、その期間または事由
- 別表の登記事項の欄に掲げる事項
Q事業年度って、いつがよいの?
医療法人の認可が出るタイミングから考えて、やはり3月決算が多いようです。
しかし、自由に設定することができますので、都合に合わせて決めることができます。
気をつけなければならないのは、認可書受領から2週間以内に登記申請しなければならないという点。
しかし、厳密にいえば【登記申請の準備が整ってから2週間】なので、必ずしも受領からカウントする必要はありません。
また、事業年度は当然1年です。
にもかかわらず、1年以上前に登記申請してしまうと、附則との関係から最初の事業年度が1年以上ということになってしまいかねません。むしろこの点に注意しましょう。
Q当法人の登記事項証明書には、解散の事由が載っていませんが。
医療法で明記されている解散事由は、登記しなくてもよいことになっています(医療法第55条第1項)。
1 定款(寄附行為)をもって定めた解散事由の発生
2 目的たる業務の成功の不能
3 社員総会の決議(社団のみ)
4 他の医療法人との合併
5 社員の欠乏(社団のみ)
6 破 産
7 設立認可の取消
なお、このうち2及び3の事由により解散する場合には、医療審議会の意見を聴いた後、県知事の認可を受けなければ、その効力は生じません(法第55、56条)。
定款に、法定以外の、たとえば「定款第○条に掲げる病院のすべてを廃止したとき」といった解散事由が記載されている場合には、登記事項証明書に「解散の事由」として明記されているかチェックしておいてください。
定款の変更
以下のような場合には、定款変更の手続が必要となります。
- 医療法人の登記事項証明書に記載されている事項を変更するとき
- 新たに診療所等を開設するとき
- 既存の診療所等を廃止するとき
- 附帯業務を開設するとき
- 附帯業務を廃止するとき
つまり、定款の条文を変更する必要がある場合には、定款変更の認可を受けなければ変更できないということです。
Q診療所建て替えのため、一時的に仮の診療所で診療を行う場合、定款変更の手続は?
必要になる可能性があります。
定款上の表記と異なる住所・所在地で診療を、一時的にでも行う場合、それに合わせて定款変更の認可申請をしなければなりません。
元に戻す際にも同様に手続が必要となるため、都合2回の定款変更手続が必要です。
「認可」手続には、通常1~2か月ほどの期間が必要となりますので、工事期間に合わせて慎重に手続を進めなければなりません。
なお、定款変更に伴って保健所への診療所開設の許可申請・届出の手続も必要となってきますし、厚生局への保険医療機関の指定も同様です。
要は、新規で法人開設の診療所を開設するのと同じ取扱いです。
Q現在の診療所から2km以上離れた場所への移転を計画中です。
定款変更と診療所移転の手続のタイミングは?
定款変更と診療所移転の手続のタイミングは?
2km以上離れた場所への移転は、保険医療機関の指定について遡及が認められません。
従って、いったん診療所を閉めたあと、あらためて開設許可申請・届出が必要となります。その間は、保険診療ができなくなってしまいますのでご注意ください。
間を空けてしまうことなく、2km以上離れた場所へ移転しようとする場合、いったん新診療所を増設し、最低1ヶ月間は併走させたのちに、旧診療所を閉める必要があります。
この方法は法人でなければ難しいうえに、一時的にですが管理者も増やさなければならないため、とてもハードルが高くなります。
2kmという距離は、「至近距離」として認められる限界ですが、場合によっては多少オーバーしても遡及の可能性はあります。
この点は、個別にご相談ください。
変更のためには、届出で済む場合もありますが、認可が必要な場合は原則として2ヶ月かかります。特に、附帯業務については様々なケースがありますので、手続を開始する前に個別に確認する必要があります。
また、定款変更は都道府県の手続だけで終わりではなく、登記に反映させるべきものについては法務局へ、診療所・病院等の変更があれば保健所や厚生局などへも手続が必要となってきます。こうした点については、各窓口では教えてくれませんので注意しましょう。
さらに、補助金などが交付されるようなケースでは、自治体との話し合いやそれぞれの手続も必要となってきます。
気をつけなければならないのは、変更中に資産総額の変更や役員変更登記がされていないなどの指導が入ることもあるということです。本来定期的に行うべきこれらの手続を怠っていた場合、さかのぼって手続しなければ定款変更がストップしてしまいます。普段チェックの入らない部分ですが、いざというときに困るわけです。日頃から適正な運営を続けていることが大切ですね。