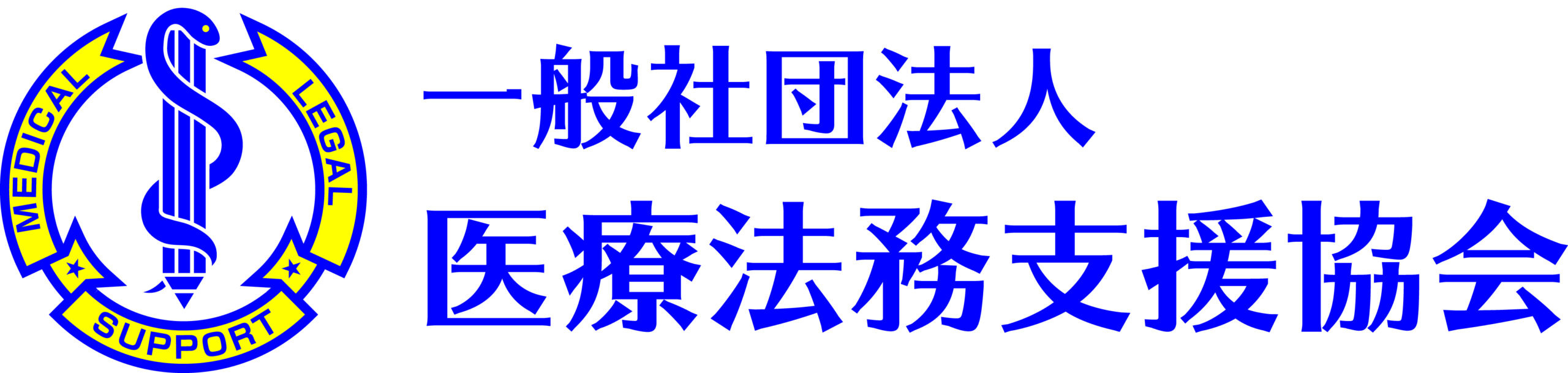医療法人には、運営の主体となるべき役員を設置します。理事長や理事、そして監事です。役員は自然人でなければならず、成年被後見人や被保佐人などは医療法人の役員になれません。
また、未成年者は望ましくないと指導するところもあり、適正な運営を確保するため第三者要件を課していることがほとんどです。事前に確認しておきましょう。
医療法人の理事・理事長
医療法人には、役員として理事3名以上、監事1名以上を置かなければなりません(法第46条の2第1項)。医療法人が開設する診療所等の管理者は、理事に就任しなければならず、管理者でなくなると理事でもなくなります(法第47条第2項)。
理事は、医療法人の常務を処理します。株式会社でいえば「取締役」の立場です。
理事長は、医療法人を代表する存在で、医療法人の業務を総理します。理事の中でも、代表権を持つのは理事長のみです。登記事項証明書(登記簿謄本)にも、理事長のみが記載されます。
そして、理事長に事故があるときや理事長が欠けたときは、定款または寄付行為の定めるところにより、他の理事がその職務を代理し、またはその職務を行うこととされています。
- Q医療法人の理事=社員?
- A
ときどき、理事の改選によって議事録上の社員まで入れ替わってしまっているケースをみかけますが、理事と社員はもちろん同一ではありません。
「医療法人の運営」もご参照ください。
- Q医療法人の理事長交代の手順
- A
理事長を、社員総会によって選任された理事による互選と規定しているケースでは、理事会で理事を改選します。
理事長の改選は登記事項ですので、法務局に変更の登記を申請します。このとき、理事長の地位のみ辞任し、理事にとどまるのであれば問題ありませんが、理事も辞任するという場合は管理者も辞任しなければなりませんのでご注意ください。
管理者の交代は保健所へも届け出る必要があり、さらに厚生局へも届け出ます。理事長のみ辞任か、理事も辞任するか。社員としてはどうか。退職はするのか、その場合退職金はどうするかなど、理事長交代の際には様々なことを検討する必要があります。医業承継にも大きく影響しますので、慎重に検討することをお勧めします。
- Q理事長以外の役員が変更となった場合は?
- A
登記事項証明書には理事長のみが登記されていますが、だからといって(平)理事や監事の変更に伴う手続がないわけではありません。
役員の選任については定款で定められています。したがって、その条文に基づいた手続を経なければなりません。当然、その記録(議事録)が必要です。
また、理事長の交代同様、管理者の変更が伴う場合(管理者は理事でなければなりません)、保健所と厚生局への届出が必要となります。
ちなみに、管理者以外の勤務医が就退任した場合はもちろん、勤務医の常勤・非常勤の変更についても、厚生局に届け出なければなりません。
このあたりは見落としがちなので、気をつけましょう。
- Q医師(歯科医師)でない者が理事長になれますか?
- A
医療法第46条の3第1項但書きで、「例外措置の運用を弾力化することにより」認められています。
非医師の理事長就任が認められるのは、次の3パターンです。① 理事長が死亡し、または重度の傷病により理事長の職務を継続することが不可能となった際に、その子女が医科または歯科大学在学中か、または卒業後、臨床研修その他の研修を終えるまでの間、医師または歯科医師でない配偶者等が理事長に就任しようとする場合
② 次に掲げるいずれかに該当する医療法人
イ 特定医療法人または社会医療法人
ロ 地域医療支援病院を経営している医療法人
ハ 財団法人日本医療機能評価機関が行う病院機能評価による認定を受けた医療機関を経営している医療法人
③ 候補者の経歴、理事会構成等を総合的に勘案し、適正かつ安定的な法人運営を損なうおそれがないと都道府県知事が認めた医療法人
- Q管理者は理事にならなければならない?
- A
はい。医療法第46条の5第6項に、以下のように規定されています。
医療法人は、その開設する全ての病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院(指定管理者として管理する病院等を含む。)の管理者を理事に加えなければならない。ただし、医療法人が病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院を二以上開設する場合において、都道府県知事の認可を受けたときは、管理者(指定管理者として管理する病院等の管理者を除く。)の一部を理事に加えないことができる。
ただし書きによる例外もあり得ますが、例外的な認可が必要となりますので、大原則として管理者=理事とお考えください。
医療法人の幹事
医療法人の役員として、監事を1名以上任命します。
監事は、医療法人の理事・従業員を兼ねることはできません(法第48条)。また、理事の親族や出資(拠出)者、当該医療法人と取引関係にある者も、監事としてふさわしいとは言えません。人選については、スムーズに手続を進めるためにふさわしい方にお願いしましょう。
- Q医療法人の監事は誰でもなれる?
- A
特にご質問の多いポイントです。
監事の人選に際しては、理事長との関係に注意が必要です。監事という役職の性質上、親族以外の第三者でなければならないと指導されることがほとんどです。なお、顧問税理士(さらにその職員)はふさわしくないと指摘されることが多く、できればそれ以外の方が就任されたほうがよいでしょう。
どこまでの親族がふさわしくないかについては、自治体ごとにばらつきがあります。他人から見て、監事としてきちんと監査できると思える人を選びましょう。
- Q医療法人の監事の役割は?
- A
従来は民法の条文が準用されていましたが、現在は医療法で明示されています。
※ 医療法第46条の4
1 (省略)
2 (省略)
3 監事の職務は次のとおりとする。
一 医療法人の業務を監査すること。
二 医療法人の財産の状況を監査すること。
三 医療法人の業務または財産の状況について、毎会計年度、監査報告書を作成し、当該会計年度終了後3ヶ月以内に社員総会または理事に提出すること。
四 第1号または第2号の規定による監査の結果、医療法人の業務または財産に関し不正の行為または法令もしくは定款もしくは寄附行為に違反する重大な事実があることを発見したときは、これを都道府県知事または社員総会もしくは評議員会に報告すること。
五 社団たる医療法人の監事にあっては、前号の報告をするために必要があるときは、社員総会を招集すること。
六 財団たる医療法人の監事にあっては、前四号の報告をするために必要があるときは、理事長に対して評議員会の招集を請求すること。
七 医療法人の業務または財産の状況について、理事に対して意見を述べること。従前よりも責任が明確にされ、医療法人の内部管理体制の強化が図られています。
また、説明が重複してしまいますが、監事はその医療法人の理事や評議員および法人の職員を兼ねることはできません(医療法第48条)。さらに、ほとんどの自治体で他の役員と親族関係がないことが必要とされています。
- Q医療法人の役員を解任することはできますか?
- A
法人にとって望ましくない人物が役員になってしまった場合、任期途中でも辞任してもらうこと、解任することが必要となる場合があります。
ところが、モデル定款を確認すると役員の選任要件については定められているものの、解任については定められていません。医療法に明確な条文がないものについては、当該医療法人の定款・寄附行為にどのように定められているかが重要です。
にもかかわらず、定款等にも明確な規定がない場合、一般法、つまり民法の委任の部分を準用することになります。民法第541条(履行遅滞等による解除権)や543条(履行不能による解除権)を準用すれば、任期途中で解任することもできますが、2年ごとの改選時に重任(再任)しないという方法がもっとも穏当でしょう。ケースごとに個別判断する必要があります。
逆に、役員や管理者を辞任したいのに、法人が拒否するというケースも少なくありません。こうした場合も、個別判断が必要となります。
- Q管理者の権限と責任
- A
医療法人に限らず、診療所の監督をする者として「管理者」を置く必要があります。管理者は、院長として当該医療機関を管理します。
管理者は、厚生労働省令で定めるところにより、医療の安全を確保するための指針の策定、従業者に対する研修の実施その他の当該病院、診療所または助産所における医療の安全を確保するための措置を講じなければならない(法第6条の10)。
なお、行政機関からの監督は、主に開設者に対して行われます。管理者を置くのは開設者の義務であり、不正等があった際に行政命令を受けるのも開設者です(法第29条)。
医療法人の場合、開設者は医療法人であり、理事が管理者となります。管理者は理事でなければなりません。
個人の場合、原則として開設者が管理者となりますが、他の者を管理者とすることもできます。